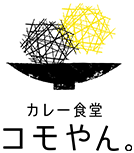甘草(カンゾウ)とは?歴史・効能・活用法まで丸ごと解説!
甘草とは、古代から多くの文化で重宝されてきたスパイス&ハーブの一種で、特有の甘みと風味が特徴です。甘草は主にその根が利用され、料理や飲み物の風味付けだけでなく、伝統医学や健康促進、美容分野でも広く活用されています。その歴史は数千年に及び、中国やインド、地中海地域をはじめ、世界各地で重要な役割を果たしてきました。甘草の甘さの秘密は「グリチルリチン酸」という成分にあり、砂糖よりも強い甘みを持ちながらも低カロリーであることから、現代の食品業界でも注目されています。本記事では、甘草の歴史や特徴、利用法、健康効果など、あらゆる角度から甘草の魅力を深掘りしていきます。
甘草とはどんなスパイス?歴史から用途まで詳しく解説!

甘草とはどんなスパイスかというと、独特の甘みを持ち、古くから薬用や食品に活用されてきたマメ科の植物です。砂糖の約50倍の甘さを持つ「グリチルリチン」という成分を含み、ハーブティーや漢方薬、スキンケア製品など幅広い用途に利用されています。特に、薬用ハーブとしての歴史は非常に長く、世界各地で消化器系のケアや喉の不調改善に用いられてきました。
甘草は、乾燥させた根が主に使用されますが、フレッシュな状態でも利用されることがあります。その独特の甘みと薬効成分により、スパイスやハーブの一種としても扱われ、さまざまな食品や飲み物、さらには医薬品の成分としても使用されています。ここでは、甘草の別名や名前の由来、植物の特徴、原産地、用途について詳しく解説します。
甘草の別名と名前の由来
甘草にはいくつかの別名があり、特に「リコリス(Licorice)」という英名で知られています。これは、ギリシャ語の「glykyrrhiza(グリキリッツァ)」に由来し、「甘い根」という意味を持ちます。この名前の通り、甘草の根は非常に甘い味が特徴で、古代から甘味料や薬として使われてきました。
また、漢方では「カンゾウ(甘草)」と呼ばれ、日本でも馴染みのある生薬の一つです。中国では「甘草(ガンツァオ)」、インドでは「ムレーティ(Mulethi)」と呼ばれ、それぞれの地域で伝統的な用途が確立されています。
甘草の別名一覧
●リコリス(Licorice)(英語名)
●グリキリッツァ(Glycyrrhiza)(ギリシャ語)
●カンゾウ(甘草)(日本語・漢方)
●ガンツァオ(甘草)(中国語)
●ムレーティ(Mulethi)(インド)
科名と植物学的特徴
甘草はマメ科(Fabaceae)に属する多年草で、草丈は1~1.5メートルに達します。根は地下深く伸びており、この部分が甘草として利用されます。植物全体は丈夫で乾燥地帯に適応しており、耐寒性も高いのが特徴です。
甘草の葉は羽状複葉で、花は紫色や青紫色の小さな花を咲かせます。花の見た目は控えめですが、植物としての生命力は非常に強く、数年間にわたって収穫が可能です。根は厚みがあり、乾燥させると硬くなりますが、甘い香りと味が際立つようになります。
原産地と栽培地域
甘草の原産地は、中央アジアや地中海沿岸地域とされています。特にトルコ、イラン、中国、インドなどが主要な産地で、これらの地域では伝統的に甘草が薬用や食品用として栽培されてきました。
現在では、ヨーロッパ、アメリカ、日本など、世界中で甘草が栽培されています。甘草は乾燥地帯での栽培に適しており、砂質の土壌を好むため、こうした環境が整った地域で広く育てられています。日本では、江戸時代から漢方薬の原料として栽培されるようになり、現在でも一部の地域で栽培が続けられています。
利用部位と加工法
甘草の主な利用部位は根です。この根は収穫後に洗浄し、乾燥させることで保存性が高まり、加工しやすくなります。甘草は粉末状、スライス状、エキス状などさまざまな形態で利用されます。
●粉末状:料理や飲み物に加えるのに便利。
●スライス状:煮出して甘草茶やスープの風味付けに利用。
●エキス状:医薬品や化粧品の原料として使用。
加工の過程で甘草の甘みを最大限に引き出すため、特定の温度や湿度で乾燥させることが重要です。
甘草の特徴
甘草の最大の特徴は、その甘みです。この甘みの源は「グリチルリチン酸」という成分で、砂糖の約50倍の甘さを持っています。この甘さは持続性があり、少量で十分な甘みを感じられるため、食品業界では天然甘味料としても利用されています。
また、甘草には特有のスパイシーで薬草のような香りがあります。この香りは料理や飲み物に深みを与えるだけでなく、リラックス効果をもたらすとも言われています。さらに、抗酸化作用や抗炎症作用が期待される成分を含むため、健康や美容にも寄与します。
甘草の用途
甘草はその甘みと効能を生かして、さまざまな分野で利用されています。
●食品・飲料
甘草キャンディーやリコリスリキュール、甘草茶などが代表的です。特にヨーロッパではリコリスキャンディーが人気で、独特の甘みと風味が特徴です。
●伝統医学
漢方薬やアーユルヴェーダでは、消化促進、抗炎症、免疫力向上の目的で使用されています。甘草は「調和薬」として、他の薬草と組み合わせて処方されることが多いです。
●化粧品
美白効果や保湿効果が期待されるため、スキンケア製品やヘアケア製品に配合されています。
●健康食品
甘草を使ったサプリメントや健康ドリンクは、現代の健康志向に応える商品として注目されています
甘草の味や香りは?奥深い甘みと独特の風味を徹底解説!

甘草の味や香りは、ただ「甘い」だけではなく、独特の奥深さと広がりを持っています。甘草(カンゾウ)は、その名のとおり強い甘みが特徴ですが、砂糖や蜂蜜の甘さとは異なり、後味が長く続くのが特徴です。特に、甘草に含まれる「グリチルリチン」という成分は、砂糖の約50倍もの甘さを持つと言われています。そのため、ごく少量でも甘さを引き出せるため、さまざまな用途で活用されています。
甘草の味の特徴とは?
甘草の味は、単なる「甘み」だけでは語り尽くせません。その甘さは優しく広がるような感覚で、口に含むとじんわりとした甘みが感じられ、後味がほんのり残るのが特徴です。また、わずかにスパイシーさやほのかな苦みを持ち合わせていることもあり、単体で摂取すると独特な風味を感じることができます。これは、甘草に含まれる天然の成分が複雑に絡み合っているためです。
例えば、甘草をそのままかじると、最初はほんのりとした甘みが広がり、次第に甘さが強まりながらも、やや薬草のようなニュアンスを感じることがあります。このため、甘草は単独で味わうというよりも、他のハーブやスパイス、食品と組み合わせることで、その持ち味を最大限に活かすことができるのです。
甘草の香りの特徴
甘草の香りは、強く主張するものではなく、ほんのりとした甘い香りが漂うのが特徴です。リコリスのような香りを持ち、どこか土っぽさやウッディな香りを感じることもあります。この独特の甘い香りは、煮出すことでさらに引き立ち、飲み物や料理に深みを与えます。
特に、甘草をお湯で煮出したり、お茶に加えたりすると、その甘くやわらかな香りが広がり、リラックス効果をもたらしてくれると言われています。このため、甘草はハーブティーや漢方薬としても広く利用されているのです。
甘草の味と香りを活かした活用法
甘草の甘みや香りは、世界中のさまざまな料理や飲み物で活用されています。例えば、中国の漢方では、他の苦い薬草の風味を和らげるために甘草が使用されることが多いです。また、日本の漢方薬でも甘草は重要な成分の一つとされています。
料理においては、スープや煮込み料理に少量加えることで、自然な甘みとコクをプラスすることができます。また、ハーブティーとして楽しむ場合は、単体でも甘みを感じることができるため、砂糖を加えずに甘草の自然な甘さを味わうことができます。特に、ショウガやシナモンなどと組み合わせると、より深みのある味わいが楽しめます。
また、甘草の甘さはスイーツにも活用され、海外では「リコリスキャンディ」として親しまれています。これは、甘草の根を抽出したエキスを使ったお菓子で、独特な甘みと香りが特徴です。日本ではあまり馴染みがないかもしれませんが、ヨーロッパではポピュラーなお菓子の一つです。
甘草の種類は?代表的な品種とその特徴を詳しく解説!

甘草の種類は、世界中でさまざまな品種が存在し、それぞれに特徴や用途が異なります。一般的に「甘草」と呼ばれるものは、マメ科の植物で、その根の部分が薬用や食品の甘味料として利用されます。最もよく知られているのは「スペイン甘草」「中国甘草」「ウラル甘草」の3種類で、それぞれ生育地や成分、風味が異なります。ここでは、代表的な甘草の種類とその違いについて詳しく解説していきます。
1. スペイン甘草(Glycyrrhiza glabra)
特徴:
スペイン甘草は、主にヨーロッパや中東で栽培されている品種で、特にスペイン、イタリア、トルコ、イランなどで広く生産されています。この甘草は「ヨーロッパ甘草」とも呼ばれ、世界中で最も広く流通している品種の一つです。
成分と風味:
スペイン甘草は、甘草の中でも特に甘みが強い品種とされ、独特のリコリス風味を持っています。そのため、リコリスキャンディや甘草茶、香料としてよく使用されます。砂糖の代わりに使われることもあり、菓子や飲料、タバコの香料としても活用されています。
主な用途:
●リコリスキャンディや甘草茶
●タバコやアルコール飲料の香料
●ヨーロッパの伝統的なハーブ薬
2. 中国甘草(Glycyrrhiza uralensis)
特徴:
中国甘草は、中国を中心に栽培され、日本や韓国、モンゴルなどのアジア諸国でも利用されています。漢方薬の主要な原料として使用されることが多く、「東洋甘草」とも呼ばれます。
成分と風味:
スペイン甘草に比べると甘さはやや控えめですが、薬効成分のグリチルリチンを豊富に含んでおり、強い抗炎症作用や抗ウイルス作用があるとされています。そのため、咳止めや胃薬、免疫力向上のための漢方薬に配合されることが多いです。
主な用途:
●漢方薬や生薬(胃腸薬、咳止めなど)
●健康茶(甘草茶や漢方ブレンドティー)
●美容・スキンケア製品の成分
3. ウラル甘草(Glycyrrhiza inflata)
特徴:
ウラル甘草は、中国北部やシベリアの寒冷地で育つ品種で、中国甘草と同じく漢方薬や健康食品として利用されることが多いです。近年では、その成分の違いから、特定の薬効を持つ甘草として注目されています。
成分と風味:
ウラル甘草には、他の甘草にはあまり含まれない「リクイリチゲニン」という成分が豊富に含まれており、特に抗酸化作用や抗炎症作用が強いとされています。味は中国甘草に似ていますが、若干の苦みを感じることもあります。
主な用途:
●漢方薬や健康食品
●免疫力向上や抗炎症作用を目的としたサプリメント
●天然の抗酸化成分を含む美容製品
4. その他の甘草の種類
上記の3種類以外にも、世界にはさまざまな甘草の品種が存在します。例えば、アメリカ甘草(Glycyrrhiza lepidota)は北米に自生し、ネイティブ・アメリカンによって伝統的な薬草として使用されてきました。また、ロシア甘草(Glycyrrhiza echinata)は東ヨーロッパやロシアで見られ、スペイン甘草に近い甘みを持つとされています。
5. 日本で使われる甘草の種類は?
日本で使用される甘草は、主に中国甘草とウラル甘草です。日本の漢方薬の約70%には甘草が含まれていると言われており、葛根湯や小青竜湯などの処方にも広く使われています。また、日本では甘草を食品の甘味料として利用することもあり、健康茶や和菓子に微量が含まれていることもあります。
甘草の歴史は?古代から現代までの活用と世界への広がり

甘草の歴史は、古代文明までさかのぼることができ、世界各地で薬草や甘味料として重宝されてきました。特に、古代エジプト、中国、ギリシャ、ローマなどの文明では、甘草の根が貴重な天然の薬として用いられ、その後、世界中へと広まっていきました。甘草は単なる甘味をもたらすだけでなく、消化を助けたり、咳を鎮めたり、さまざまな健康効果があるとされ、今日に至るまで医療や食品、化粧品など幅広い分野で利用されています。ここでは、甘草の歴史を古代から現代にかけて詳しく解説していきます。
1. 古代エジプトと甘草 – ファラオも愛した万能薬
甘草の使用が記録として最も古く残っているのは、古代エジプトです。紀元前3000年ごろのエジプトの医学文献「エーベルス・パピルス」(紀元前1500年頃)には、甘草が薬草として記載されており、主に消化器系の不調や咳止め、炎症の治療に使われていました。
また、有名なツタンカーメン王の墓からも甘草の根が発見されており、王族たちが甘草を健康維持のために愛用していたことが分かっています。エジプトでは甘草の根を煮出して甘い飲み物(現在の「リコリスティー」に相当)として摂取し、暑さ対策や体調管理に利用していたとされています。
2. 古代中国と甘草 – 漢方薬の重要成分としての発展
甘草は、中国でも非常に長い歴史を持つ薬草の一つです。中国最古の薬物書『神農本草経』(紀元前200~200年頃)には、甘草が「上品(最も優れた薬草)」として分類されており、「百薬の毒を解し、五臓を調える」と記されています。これは、甘草が単独でも優れた効能を持ち、他の薬草の働きを調整する作用があると考えられていたためです。
その後、甘草は漢方薬の基本的な生薬の一つとなり、日本の漢方医学にも大きな影響を与えました。例えば、葛根湯(かっこんとう)や小青竜湯(しょうせいりゅうとう)など、多くの漢方薬には甘草が含まれています。
また、中国では「炙甘草(しゃかんぞう)」と呼ばれる特別な甘草の加工方法も発展しました。これは、甘草の根を蜂蜜とともに炒ることで、より効果を高める手法です。これにより、甘草の甘みが増し、より消化器系への作用が強くなるとされています。
3. 古代ギリシャ・ローマと甘草 – 医学の父・ヒポクラテスも使用
甘草は、紀元前のギリシャ・ローマ時代にも医薬品として利用されました。ギリシャの医師ヒポクラテス(紀元前460〜370年)は、甘草を咳止めや胃腸の不調を和らげる薬として用いたとされており、その後、ローマ帝国でも広く活用されました。
また、ローマの博物学者プリニウス(23~79年)も、著書『博物誌』の中で甘草の効能を記録しており、「喉の渇きを抑える効果がある」と述べています。このため、ローマ軍の兵士たちは砂漠を行軍する際に甘草を持ち歩き、水分補給が難しい環境でも耐えられるようにしていたと伝えられています。
さらに、ローマでは甘草の甘味成分を生かし、飲料や菓子の甘味料としても利用されていました。この流れが後のヨーロッパに伝わり、リコリスキャンディの文化が生まれることになります。
4. 中世ヨーロッパ – 薬草学と甘草の普及
中世ヨーロッパでは、修道院が薬草学の中心となり、多くの薬草が研究・栽培されました。甘草もその一つで、消化不良、のどの痛み、風邪の治療などに利用されました。特に、修道院で作られる薬草酒(リキュール)にも甘草が加えられることが多く、ヨーロッパ全土に広がっていきました。
16世紀には、イギリスやフランスでも甘草が栽培されるようになり、イギリスのポンテフラクト地方では、17世紀に「ポンテフラクト・ケーキ」と呼ばれる甘草を使った黒いキャンディが誕生しました。これは、現代のリコリスキャンディの元祖とも言われています。
5. 近代から現代 – 医療・食品・美容へと広がる甘草の役割
近代に入ると、甘草は医薬品の原料として本格的に研究されるようになりました。19世紀には、甘草の有効成分「グリチルリチン」が発見され、消炎作用や抗ウイルス作用があることが確認されました。これにより、甘草は風邪薬や胃薬、皮膚炎治療薬などに幅広く使用されるようになりました。
また、甘草エキスは食品業界でも活躍し、ソフトドリンクやアルコール飲料、菓子の甘味料として利用されるようになりました。特にアメリカでは、コカ・コーラの初期のレシピにも甘草が含まれていたと言われています。
さらに、現代では美容業界でも甘草が注目されており、美白効果や抗炎症作用を活かした化粧品やスキンケア製品に多く含まれています。甘草由来の成分は、シミやくすみを抑える効果があるため、自然派化粧品の成分として人気を集めています。
甘草の保存方法は?長持ちさせるためのコツと最適な保管方法

甘草の保存は、適切な方法を取ることで品質を長く保つことができます。甘草は、乾燥させた根の形で販売されることが多く、そのまま保存する場合と粉末やエキスに加工されたものを保存する場合で方法が異なります。また、湿気や直射日光を避けることが重要であり、保存環境によって甘草の風味や効能が変化してしまうこともあります。ここでは、甘草をできるだけ長持ちさせるための保存方法について詳しく解説します。
1. 甘草の保存に適した環境とは?
甘草は湿気を吸収しやすいため、適切な環境で保管しないと品質が低下する恐れがあります。保存に最適な環境は以下のような条件です。
✅ 湿気を避ける:乾燥した場所で保存することが大切。湿気が多いとカビや変色の原因になる。
✅ 直射日光を避ける:紫外線によって甘草の有効成分が分解されることがあるため、暗い場所で保管する。
✅ 気温の変化が少ない場所:急激な温度変化は甘草の品質に影響を与えるため、一定の温度を保てる場所が理想的。
✅ 密閉容器に入れる:空気に触れると風味や有効成分が失われやすいため、密閉容器に入れて保存するのが望ましい。
2. 甘草の形状別・最適な保存方法
① 乾燥甘草(スライス・チップ・スティック)の保存
乾燥させた甘草の根は、比較的保存が効く形状ですが、湿気や直射日光の影響を受けやすいため、次のような方法で保存するとよいでしょう。
🔹 密閉容器(ガラス瓶・保存袋)で保存:乾燥剤と一緒に入れておくと、湿気を防げる。
🔹 冷暗所に保存:直射日光を避け、風通しの良い場所に置く。
🔹 冷蔵庫や冷凍庫での保存も可:長期保存したい場合は、冷蔵庫の野菜室や冷凍庫に入れるのもおすすめ。ただし、解凍時の結露で湿気を含む可能性があるため、使う分だけ取り出すようにする。
▶ 保存期間の目安
●常温保存(密閉容器):約1年
●冷蔵保存(密閉容器):約2年
●冷凍保存(密閉容器):約3年
② 粉末甘草(パウダー)の保存
粉末状の甘草は、乾燥甘草よりも湿気を吸収しやすく、風味や効能が劣化しやすいです。そのため、特に湿気対策を徹底することが重要です。
🔹 乾燥剤と一緒に密閉容器に入れる:湿気を防ぎ、固まりを防ぐためにシリカゲルなどの乾燥剤を入れる。
🔹 冷暗所で保存:風通しの良い場所に置き、湿気を避ける。
🔹 冷蔵庫・冷凍庫での保存は控える:粉末は温度差による結露が発生しやすいため、冷蔵庫や冷凍庫での保存はあまりおすすめできない。
▶ 保存期間の目安
●常温保存(密閉容器):約6か月〜1年
③ 甘草エキス・シロップの保存
甘草を煮出したエキスやシロップは、液体であるため保存方法が異なります。
🔹 冷蔵保存が基本:清潔な瓶に入れ、冷蔵庫で保存する。
🔹 冷凍保存も可能:製氷皿に入れて小分けにし、凍らせると使いやすい。
🔹 砂糖やアルコールを加えて保存性を高める:エキスに蜂蜜やリキュールを加えることで、保存期間を延ばすことができる。
▶ 保存期間の目安
●冷蔵保存:約1週間
●冷凍保存:約1か月
3. 保存中に甘草が劣化するサイン
保存中の甘草に次のような変化が見られたら、品質が劣化している可能性があります。
⚠ カビが生えている → 湿気が多すぎる可能性。すぐに処分する。
⚠ 色が変わった(黒ずみ・変色) → 酸化や劣化のサイン。
⚠ 異臭がする → 保存環境が悪いか、腐敗の可能性がある。
⚠ 風味が落ちた → 甘みが薄くなった場合、保存期間が長すぎる可能性。
もしこれらの症状が見られた場合は、使用を避けるか、新しいものと交換するのが望ましいでしょう。
甘草の魅力とは?奥深い甘みと健康効果で古くから愛される万能ハーブ

甘草の魅力は、その独特の甘みと幅広い健康効果にあります。古代から薬草として利用されてきた甘草は、ただの甘味料としてだけではなく、身体の調子を整える作用があることから、世界中で医薬品や食品、さらには美容製品にまで活用されてきました。ほんの少量でもしっかりとした甘みを感じられる特性を持ち、砂糖の代わりとしても優れた働きをするため、現代でもさまざまな形で私たちの生活に取り入れられています。ここでは、甘草の持つ甘みの秘密や健康・美容効果、さらに活用方法など、その魅力を詳しく紹介します。
1. 甘草の魅力① – 砂糖の50倍の甘みを持つ自然の甘味料
甘草の最大の特徴は、「グリチルリチン」という成分による強い甘みにあります。このグリチルリチンは、砂糖の約50倍の甘さを持ちながらも、後味がスッキリとしており、少量でも十分な甘さを感じられるのが特徴です。そのため、甘草は古くから天然の甘味料として利用されてきました。
また、砂糖のように血糖値を急激に上昇させることがないため、健康を意識する人々にとっても魅力的な甘味料の一つです。特に、糖分を控えたい人や、ナチュラルな甘みを求める人にとって、甘草は理想的な選択肢となるでしょう。
甘草の甘みの特徴
✅ 砂糖の約50倍の甘さを持つ
✅ 少量でもしっかりとした甘みを感じられる
✅ 血糖値を急激に上げにくい
✅ 後味がスッキリとしている
2. 甘草の魅力② – さまざまな健康効果で体をサポート
甘草は単なる甘味料ではなく、優れた薬効成分を含むハーブでもあります。特に、漢方やハーブ療法では、「万能薬」として広く用いられ、胃腸の調子を整えたり、炎症を抑えたりする働きがあるとされています。
① 胃腸の調子を整える
甘草には、胃の粘膜を保護する作用があるため、胃の不調を改善する効果が期待できます。例えば、胃痛や胃もたれ、食べ過ぎによる不快感を和らげるために、漢方薬や健康茶に甘草が配合されることが多いです。
② 炎症を抑え、喉や肌の健康をサポート
甘草に含まれるグリチルリチンは、強い抗炎症作用を持ち、風邪や喉の痛み、さらにはアレルギー症状を緩和する働きがあります。そのため、甘草は咳止めシロップやのど飴の成分としてもよく使われています。
また、肌荒れや炎症を抑える作用もあるため、スキンケア製品にも活用されており、敏感肌の人でも安心して使える成分として注目されています。
③ ストレスや疲労を和らげる
甘草には、副腎の働きをサポートし、ストレス耐性を高める効果があると言われています。特に、過度なストレスや疲労を感じているときに、甘草を含んだハーブティーを飲むことで、リラックスしやすくなるとされています。
甘草の健康効果まとめ
✅ 胃腸を守り、消化を助ける
✅ 炎症を抑え、喉や肌の健康をサポート
✅ 風邪予防やアレルギー対策に役立つ
✅ ストレスや疲労を和らげる
3. 甘草の魅力③ – 美容やスキンケアへの活用
甘草は、美容の分野でも注目されているハーブの一つです。特に、美白効果や肌荒れの改善に役立つとされ、多くの化粧品やスキンケア製品に配合されています。
① 美白効果で透明感のある肌へ
甘草に含まれるグラブリジンという成分には、メラニンの生成を抑える働きがあり、シミやくすみの改善に役立ちます。そのため、甘草エキスは美白化粧品に広く使用されています。
② 肌トラブルを防ぐ抗炎症作用
ニキビや赤み、肌荒れが気になる場合にも、甘草の抗炎症作用が役立ちます。敏感肌の人向けのスキンケア製品にも配合されることが多く、肌への刺激が少ないのも特徴です。
甘草の美容効果まとめ
✅ 美白効果でシミ・くすみを防ぐ
✅ 肌荒れや炎症を鎮める
✅ 敏感肌の人でも使いやすい成分
4. 甘草の魅力④ – 幅広い活用方法で楽しめる
甘草は、食品・飲料・スキンケア・漢方薬など、多くの場面で活用されています。以下のような方法で、日常生活に取り入れることができます。
① 甘草茶として楽しむ
甘草をお湯で煮出して甘草茶にすると、ほんのりとした甘みがあり、リラックス効果も期待できます。単体でも楽しめますが、ショウガやシナモンとブレンドすることで、より深みのある味わいになります。
② 漢方薬や健康食品として取り入れる
甘草は、葛根湯や小青竜湯など、多くの漢方薬に含まれています。サプリメントとしても販売されているため、手軽に健康管理に役立てることができます。
③ 料理やお菓子にプラス
甘草は、海外ではリコリスキャンディとして親しまれていますが、スープや煮込み料理に少量加えることで、自然な甘みとコクをプラスすることができます。
甘草を使ったレシピ
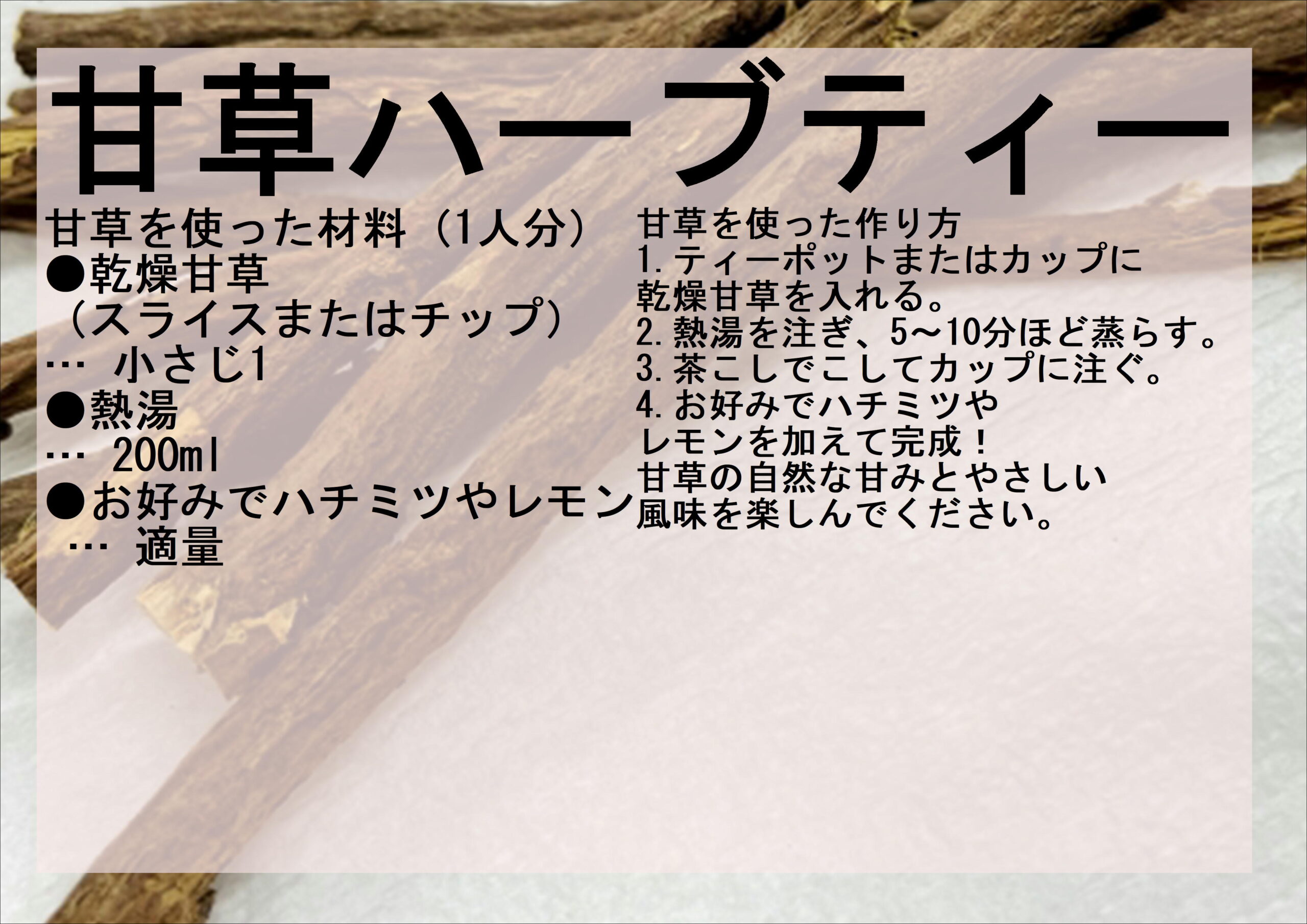
甘草を使ったレシピは、ほんのり甘く奥深い風味が楽しめるのが魅力です。今回は、甘草を使った「甘草ハーブティー」の作り方を紹介します。リラックスしたいときや喉をいたわりたいときにぴったりです。
甘草を使った材料(1人分)
●乾燥甘草(スライスまたはチップ)… 小さじ1
●熱湯 … 200ml
●お好みでハチミツやレモン … 適量
甘草を使った作り方
1.ティーポットまたはカップに乾燥甘草を入れる。
2.熱湯を注ぎ、5〜10分ほど蒸らす。
3.茶こしでこしてカップに注ぐ。
4.お好みでハチミツやレモンを加えて完成!
甘草の自然な甘みとやさしい風味を楽しんでください。